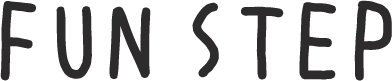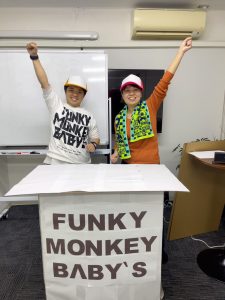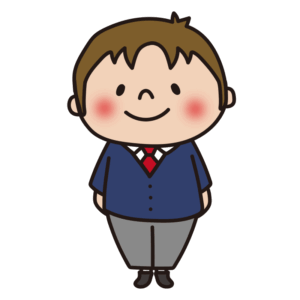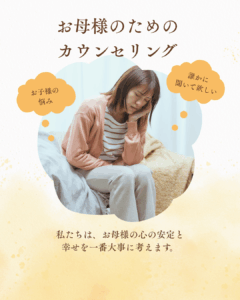「生きづらいな」「違和感がある」生活の中でそんなことを感じたことはありませんか?
周りのみんなは出来ているのに自分はうまく出来ない。
学校や職場、いきずらいなと感じたり、お子さんから相談されたりしたことありませんか?
コミュニケーションや社会的なやりとりが苦手
集中力が続かず、気が散りやすい
知的発達には問題がないが、特定の分野でつまずきやすい
生活の中で感じる「生きづらさ」「違和感」少しでも心が軽くなるように解決していきましょう!
個性?それとも欠点?
他の人ができているのに自分は出来ない・・・
他の人と違うことをしてしまう・・・
はじめに、完璧にできた人間なんてこの世にいません。
みんな得意、不得意あると思います。
「発達障害」昔はなかなか理解されることのなかったものだと思います。
「自分勝手」「わがまま」「困った子」などと捉えられ、「怠けている」「親の育て方が悪い」など
と批判されることも少なくなかったのではと思います。
日本では、発達障害の傾向がある人は約10人に1人といわれています。
大体の人が何かしらの欠陥を持っているということです。
その欠陥により生活ができないくらい困る人もいれば、なんともない人もいてます。
発達障害の診断基準は細かく難しく一概に「障害」があるとは言えないのが現状です。
グレーゾーンと呼ばれる人もいます。
生活するのに支障が出るくらい困っていても発達障害とは診断されるとは限らないのです。
とても難しいラインです。
周りからしてみれば特にどうってことないことも自分はすごく気にしていたりで・・・
障害というラインすら曖昧で神経発達のずれや脳の機能不全が原因であると考えられており、
病気ではないため治療や根絶を目指すものではないため
お薬をのんだから、治療をしたからと必ず劇的に変わるものではありません。
当事者が気になら生活もうまく行っているのであれば考える必要のないことですが、
悩んでいる方このブログで心が少しでも軽くなればと思います。
基本的な理解が大切
お子さんが発達障害と診断されたり、発達に特性があるのでは?と感じたとき、親も当事者も「理解」が大切です。
捉え方、考え方次第で当事者も家族も変わってくると思います。
こうでなければならないという固定概念で縛りつけてはいけません。
なぜそんなことも出来ないの?ではなく相手に合わせて待ってあげる。
もどかしい気持ちにはなりますが辛抱強く待ってあげることも大切です。
どのような症状があるの?
自閉スペクトラム症(ASD)
・コミュニケーションや社会的なやりとりが苦手
・こだわりが強く、特定のルーチンや物事に執着しやすい
・感覚の過敏・鈍麻(音や光、触覚などに対する感じ方が人と異なる)
注意欠如・多動症(ADHD)
・集中力が続かず、気が散りやすい
・落ち着きがなく、じっとしているのが苦手
・計画的に行動するのが難しく、忘れ物が多い
学習障害(LD)
- 読む、書く、計算するといった特定の学習分野で困難を抱える
- 知的発達には問題がないが、特定の分野でつまずきやすい
上記のような症状があったとしても必ずしも発達障害があるとは限りません。
大きく3つの発達障害ついて記載しました。
症状を見てみると自分のもなんだか当てはまるかもと感じる部分もあるかもしれません。
発達障害は決めつけるものではありません。
基本的なサポート

特性を理解し、受け入れる
まず大切なことは受け入れ理解すること。
「しつけ」や「育て方」では対応が難しいことがあります。
「なぜこの行動をするのか?」を理解し、叱るのではなく、その子の特性に合わせたサポートを考えていくことが重要です。
発達障害に限らず「怒って叱る」というのはあまり効果的ではありません。
感情をぶつけても伝わるなければ意味がありません。
なぜ怒られているのか?注意されているのか?
発達障害がある人は伝わりにくい場合があります。
根気よく伝えていくというのが大切です。
例えば廊下を走る子供に走ってはいけませんと怒ってもなかなかゆうことを聞いてくれない。
なぜ走ってはいけないかを理解してもらわないといけないです。
走る足を止めてもらって「走ったら危ないよ!一緒に歩こう」と
なぜダメなのかとどうしたらいいかの正解を伝えてあげる。
発達障害に限らず理解してもらえるように伝えるというのはとても大切なことです。
本人だけでなく周りの伝え方もとても大切です。
欠点ではなく特性や個性と捉えることも大切です。
例えば、ASDの子どもが特定の行動にこだわる場合、それを無理にやめさせるのではなく、「どのように取り入れるか」を工夫すると良いでしょう。
また、ADHDの子どもが忘れ物をしやすい場合、視覚的なチェックリストを活用するなど、環境を整えることで対応できます。
関わり方考え方を周りの大人も変えていくことが大切です。
発達障害は「生きづらさ」につながることもありますが、適切なサポートがあれば、その人の能力を最大限発揮できます。
家族の向き合い方
「普通」ではなく「個性」を大切にする
「〇〇ができない」「他の子と違う」と思うことがあるかもしれませんが、発達障害のある子どもには、独自の強みや特性があります。
できないことに目を向けるのではなく、「この子の得意なこと」「好きなことは何か」を意識すると、子ども自身の自己肯定感が育ち
失敗をしても挑戦する力がつきます!
できることを少しずつ増やす「スモールステップ」の考え方
一度に大きな目標を設定するのではなく、「今日はこれができた」「昨日よりもスムーズにできた」と小さな成長を認めることが大切です。親が焦らず、一歩ずつ進める気持ちを持つことで、子ども自身も安心してコツコツ成長できます。
もどかしい気持ちもありますが成長感じると嬉しいですよね!
親自身も「完璧」を目指さない
もっと良い対応をしなければ」「ちゃんと育てなければ」とプレッシャーを感じすぎると、親自身が疲れてしまいます。
子育てに正解はありません。ときには「まあいいか」「今日はうまくいかなかったけど、大丈夫」と肩の力を抜くことも大切です。
焦りや、イライラなどの感情は子供にも映ります。
思い詰めすぎず周りに頼ったり一人で抱え込まなにようにしましょう。
子どもと一緒に学ぶ姿勢を持つ
発達障害の特性や支援方法について学ぶことで、より良い接し方が見えてきます。
しかし、「親がすべて理解しなければ」と気負いすぎる必要はありません。
専門家や支援者の力を借りながら、「親も子どもと一緒に成長する」という気持ちでいることが大切です。
気持ちを言葉にする
ストレスをため込むと、親自身の健康にも影響を与えてしまいます。身近な人に話すだけでも気持ちが軽くなることがあります。
- 「今日はしんどかった」と家族や友人に話す
- 支援者やカウンセラーに相談する
- 日記を書く、SNSで発信する(匿名で話せる場を活用する)
「今できること」に目を向ける
「将来どうなるのか」「この先ずっと大変なのか」と不安に思うこともあるでしょう。しかし、先のことを考えすぎると、ストレスが大きくなってしまいます。
「今、この子にとって必要なことは何か?」と考え、目の前の一歩に集中することで、不安を和らげることができます。
最後に
何もかも完璧な人はいません。
向き不向き必ずあります。
たまたみんなが簡単にできることが苦手なだけで
他の部分で才能が開花するかもしれません。
不安な将来を考えよりも、今できることを一緒に考えていきましょう!
考え方・捉え方次第で世界は180度変わります!
IPELではみなさんの個性を伸ばし、サポートも行っております!
一緒に得意を伸ばしていきましょう!