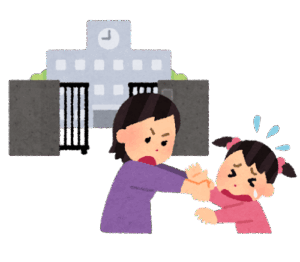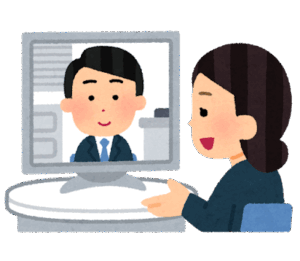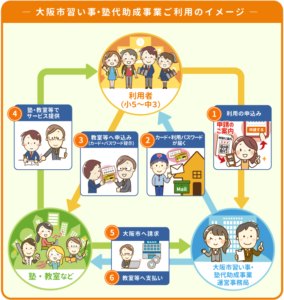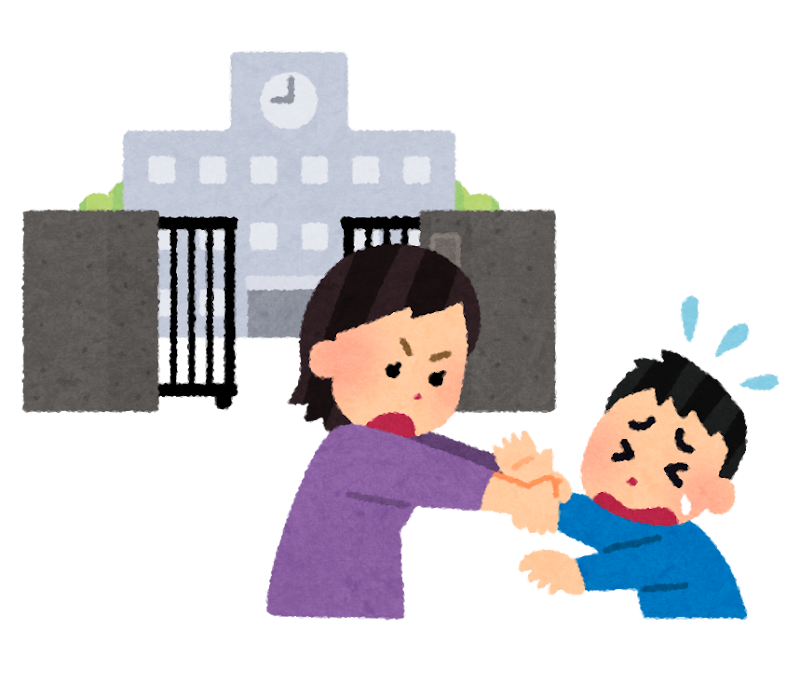
〜よくある原因と親の対応のヒント〜
不登校は「甘え」でも「怠け」でもなくて、心や体が「もう無理かもしれない」とSOSを出しているサイン。
男の子の場合は特に「言葉にして助けを求める」ことが苦手な子も多く、原因や背景が分かりづらいこともあります。
けれど、少しずつでも理解して寄り添うことで、安心と信頼が育ち、また自分らしく歩き出す力になっていきます。
よくある不登校の原因(男の子編)

学校での人間関係の悩み
男の子は「自分の立ち位置」や「仲間内の力関係」にとても敏感。
いじめとまではいかなくても、グループに馴染めないことや、友達との些細なズレが大きな不安につながることがあります。
「うまく会話に入れない」「友達が突然冷たくなった気がする」など、小さなことが積み重なって、やがて学校が怖くなってしまうことも。
先生との関係や叱られ体験
男の子は自尊心が強い一方で、繊細な一面も持っています。
先生からの注意や叱責を「否定された」と受け取って、心に深く傷を残してしまうことも。
その場では平気そうに見えても、実は心の中で「もう行きたくないな…」と静かに感じていたりします。
学業へのプレッシャーや苦手意識
勉強が得意でない子は「どうせやっても無理」「自分だけができない」と感じやすく、自信をなくしやすくなります。
小学校高学年から中学生にかけては、周囲との学力差が気になり始める時期でもあり、「劣等感」が登校意欲を奪ってしまうこともあります。
家庭環境の不安定さ
家庭の中に安心感がないと、学校どころではなくなってしまいます。
両親の仲が悪い、家の中にトラブルがある、あるいは過干渉・放任など、家庭環境も不登校の大きな要因になり得ます。
親からの期待や、逆に無関心なども、子どもの心に影響を与えることがあります。
発達特性・グレーゾーンのしんどさ
見た目では分からないけれど、ASD(自閉スペクトラム)やADHDの傾向がある子は、「集団での生活がとにかく苦しい」と感じていることがあります。
音や光、人との距離感など、さまざまな刺激に敏感で、知らず知らずのうちにストレスを溜め込んでしまうケースも。
信頼関係を育むために大切なこと
「この子は大丈夫」と信じること
子どもが一時的に学校へ行けなくなっても、人生が終わるわけではありません。
まずは「大丈夫。今は休む時期だね」と信じてあげること。
親が信じてくれているだけで、子どもはホッとできるし、自分を責めすぎずにいられます。
安心できる家を「心の避難所」にする
家の中では「なにがあってもあなたの味方だよ」というメッセージを伝え続けることが大切。
「学校に行かない=失敗」ではなく、「今はそういう時期なんだね」と自然に受け止めてあげるだけで、子どもは自分を守れるようになります。
無理な登校の促しは逆効果
「いつから行くの?」「早く元に戻ってよ」という声かけは、プレッシャーや罪悪感を生みやすく、さらに心を閉ざす原因になります。
それよりも「今日はどんなふうに過ごしたい?」「何かしたいことある?」と、自分の意思を尊重されることが、安心と自立の第一歩になります。
日常会話や“楽しい共有”を増やす
いきなり「理由を話してごらん」と言っても、子どもはなかなか話せません。
ゲーム、アニメ、音楽、好きな食べ物など…子どもの「好き」に寄り添い、同じものを一緒に楽しむ時間が、自然な信頼関係を育てていきます。
親も「がんばりすぎない」ことが大切
親も不安でいっぱいだと思います。でも、無理をしすぎると親の疲れや不安は必ず子どもにも伝わってしまいます。
親自身も、気持ちを吐き出せる相手や、ほっとできる時間を持ってほしいです。
笑顔の親がそばにいること、それが何よりの支えになるんです。
当スクールでは、全く家から出られなかった子が、新大阪の教室まで通えるようになる秘密があります!
ご興味ある方はお問い合わせくださいね!
問い合わせは
LINE
もしくは
お問い合わせフォームから
お気軽にご相談くださいね!