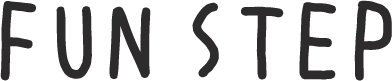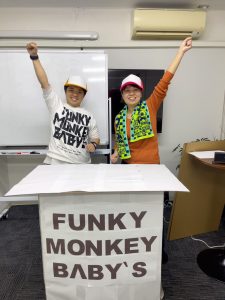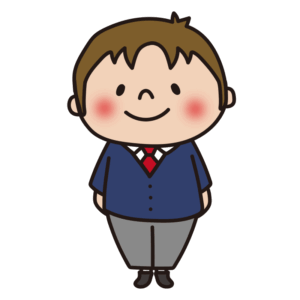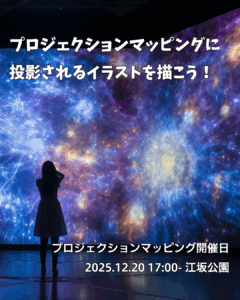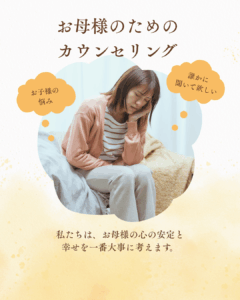こんにちは!
大阪で不登校支援/引きこもり支援をしているFun Step school(IPEL)です。
この記事では、「不登校の子どもの進路が不安」「どこに相談したらいいのか分からない」と悩む保護者や本人に向けて、2025年時点での最新の進路相談情報をわかりやすくまとめてお届けします。
文部科学省の統計によると、2023年度には全国で約29万人(※)の小中学生が不登校と報告されており、35人に1人という割合にまで増えています。
こうした背景からも、進路について早めに知識を持つことはとても大切です。
(※出典:文部科学省 不登校に関する調査結果)
今回は、進学や就職などの進路パターン、利用できる公的支援、そしておすすめの相談先について解説していきます。
不登校の進路に悩んだらまず確認したいこと
不登校でも進路選択はできる
「不登校=進学できない」と誤解されがちですが、実際にはさまざまな進路の選択肢があります。
- 通信制高校
- 定時制高校
- 不登校特例校
- サポート校
- 高卒認定試験(旧大検)
- 就労支援・職業訓練 など
進学・就職どちらも可能で、「学校に通わなかったから進路が狭まる」ということはありません。
大切なのは、子どもの現状や希望に合った選択肢を見つけることです。
出席日数や成績が心配な場合
中学卒業後の高校進学では、出席日数や内申点が選考基準に含まれることが多いため、不登校の影響を心配する声もあります。
ですが、通信制高校や一部の私立高校、不登校特例校では「個別の事情を考慮する入試」が行われており、不登校を理由に門前払いされることは基本的にありません。
また、内申書に「不登校であること」がそのままマイナス評価になることはなく、文部科学省も教員に対し、出席できなかった理由や努力した点を適切に記述するよう求めています。
不登校からの進学パターン
通信制高校とは?
通信制高校は、自宅学習を中心に、年数回のスクーリング(登校日)だけで卒業を目指せる高校です。
特徴
- 自分のペースで学べる
- 登校日が少ないため通学が負担になりにくい
- 高校卒業資格が得られる(全日制と同等)
どんな人に向いている?
- 学校に通うことに強い不安がある
- 生活リズムを自分で整えたい
- アルバイトや趣味と両立したい
最近はオンライン授業の対応が進んでおり、全国どこにいても質の高い学びが受けられる学校も増えています。
サポート校って何?
サポート校とは、通信制高校と連携しながら学習や生活面を支援する民間の教育機関です。
メリット
- 学習のフォローアップが手厚い
- 登校頻度や学び方を柔軟に選べる
- 進学や就職の相談も可能
ただし、授業料がかかる点には注意が必要です。家庭の経済状況によっては、公的な就学支援金の利用を検討しましょう。
不登校の進路相談はどう進める?親子でできるステップ
ステップ1:今の状況を一緒に整理する
まず大切なのは、お子さんの現在の心身の状態や希望、得意・不得意などを一緒に整理することです。
- 学校に通えない理由(人間関係、学習への不安、体調など)
- 学びたい意欲はあるかどうか
- 将来的に興味のあること
- 一日の生活リズムや行動パターン
これらを客観的に把握することで、今後どのような進路が合っているかのヒントが得られます。
ステップ2:信頼できる相談機関を見つける
不登校の進路に関する相談は、1人で抱え込まず、外部の専門機関や支援者に相談することが大切です。
次のような公的・民間の機関が利用できます。
不登校の進路相談ができる主な相談先
教育支援センター(適応指導教室)
各自治体の教育委員会が運営する相談・学習支援施設です。
「適応指導教室」とも呼ばれ、学習支援だけでなく、生活リズムの改善や人との関わりを取り戻す練習の場として活用されています。
特徴
- 登校に不安のある子どもが無理なく通える
- 心理士や支援員が常駐していることも多い
- 学校との連携が取りやすい
注意点
- 通える地域が限られるため、自治体ごとの確認が必要
学校・担任・スクールカウンセラー
在籍校の担任やスクールカウンセラーに相談することも第一歩になります。
文部科学省のガイドラインでは、担任が不登校の生徒に対して継続的な関わりを持つよう推奨されています。
- 学校からのサポートや配慮について聞ける
- 進路選びで不利にならないよう対応してもらえることも
「話しにくい」と感じる場合は、まずは保健室の先生や教頭など、話しやすい人から始めてみましょう。
児童・生徒支援センター(子ども家庭支援センターなど)
厚生労働省の支援制度のもと、地域の「子ども家庭支援センター」などでも進路に関する相談が可能です。
- 心理面・家庭環境も含めた支援が受けられる
- 専門スタッフによる家庭訪問もあり
民間のフリースクール・教育支援団体
近年は、NPO法人や民間団体が運営するフリースクールや教育支援サービスも全国に増えてきました。
活用メリット
- 子どもに合ったペースで学べる
- 同じ境遇の仲間と出会える
- 進路のサポートも一貫して対応してくれる
例えば、「カタリバ」「東京シューレ」「NPO法人登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク」などが代表的です。
公的な支援制度も活用しよう
就学支援金制度(通信制・私立高校など)
経済的な負担を軽減するための制度です。
通信制高校や私立高校への進学でも、一定の条件を満たせば国から授業料の補助を受けられます。
参考:文部科学省「高等学校等就学支援金制度」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka
高卒認定試験の支援制度
高校を卒業しないまま社会に出たい場合、「高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)」を活用する選択肢もあります。
高卒認定に合格すれば、大学・短大・専門学校への進学や、就職時の「高卒」扱いが可能になります。
また、受験生向けに対面・オンラインの無料講座を行っている自治体やNPOもあります。
不登校から進路を見つけた事例紹介
進路選びのヒントとして、不登校を経験した人たちがどのような進路を選び、どう歩み始めたかの具体例を紹介します。
事例1:通信制高校で自分を取り戻したAさん(中学不登校 → 通信制 → 大学)
中学1年から不登校になったAさんは、自宅で過ごす日々が続いていました。
中学3年時に教育支援センターの相談をきっかけに、通信制高校の個別相談会に参加。
本人の「人と関わるのはまだ不安」という気持ちを尊重し、登校回数が少ない学校を選択。
最初はオンライン授業中心でしたが、徐々に自信をつけ、大学進学も果たしました。
ポイント: 本人の「今できること」に合わせて進路を設計したのが成功のカギ。
事例2:不登校特例校で安心して通学できたBさん(中学不登校 → 特例校 → 専門学校)
Bさんは人間関係のトラブルで中学2年から不登校に。
地元に新設された不登校特例校の情報を知り、保護者と見学へ。
「みんなが不登校経験者」という安心感から、無理なく通えるように。
特例校では自分のペースで学べるだけでなく、心理的なケアやキャリア教育も行われ、卒業後はデザイン系専門学校へ進学しました。
ポイント: 同じ境遇の仲間がいる環境が自己肯定感の回復につながった。
事例3:高卒認定とアルバイトで自立を選んだCさん(高校中退 → 高卒認定 → 就職)
Cさんは高校に入学したものの、ストレスから1年で中退。
「自分のペースで勉強したい」という思いから高卒認定の勉強を開始。
並行してアルバイトを始め、自立心と社会経験を積みながら1年半で全科目合格。
現在はIT企業で契約社員として働いています。
ポイント: 無理に「高校在学」にこだわらず、自分の納得できる方法を選んだ。
不登校の進路選びで大切にしたいこと
「今できること」をベースに進路を考える
不登校の進路選びで最も大切なのは、「理想」ではなく「現実に合った一歩」を選ぶことです。
- 今、毎日登校できなくてもOK
- 勉強が遅れていても、やり直せる場はある
- 自分のペースで前に進める環境がある
「みんなと同じ進路」でなくていい。「自分に合った進路」を選ぶことが、将来の幸せにつながります。
保護者ができるサポート
- 子どもに無理をさせないこと
- 焦らず、長い目で見守る姿勢
- 第三者(支援機関など)との連携
子ども自身が進路を決めていくには、時間が必要です。
「今は動けない」という時期も含め、子どもの可能性を信じてサポートすることが、結果的に良い進路選びにつながります。
まとめ
不登校であっても、進路の選択肢は数多くあります。
- 通信制・定時制高校、不登校特例校
- サポート校やフリースクール
- 高卒認定試験
- 就労支援や民間のキャリア支援 など
文部科学省や各自治体も、多様な学びの場や支援制度を整備しています。
一人で悩まず、まずは信頼できる相談先を見つけることから始めてみてください。
この記事が、少しでも不登校の子どもと保護者の方の参考になれば幸いです。
進路についてのご質問や不安がある方は、地域の教育委員会、学校、支援機関にぜひ相談してみてください。